2010年05月30日
文化活動の実践
~北海道文化財保護協会は、道内の有形・無形の残すべき文化遺産を、社会資本として次世代へ引き継ぐために活動しています。
平成22年度、通常総会と文化財めぐり
~平成22年6月5日(土)
11:00~12:00 通常総会かでる2・7ビル、10F
13:30~16:50 文化財めぐり
○北大古河講堂、農学部本館 、総合博物館ほか
(バスで、移動)
○ サッポロビール博物館等
17:00~19:00 情報交換会(懇親会)
○サッポロビール園
~子ども達へ伝えたい「北海道の歴史と文化」
もっと知ろう、残そう郷土の歴史語り
北海道文化財保護協会
(Tel&Fax 011-271-4220/Mail Address:bunho@abelia.ocn.ne.jp)へ入ろう
第182号 上藻別駅逓保存会が手作り郷土賞 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
情報交換会資料1/2~地域活動の実践
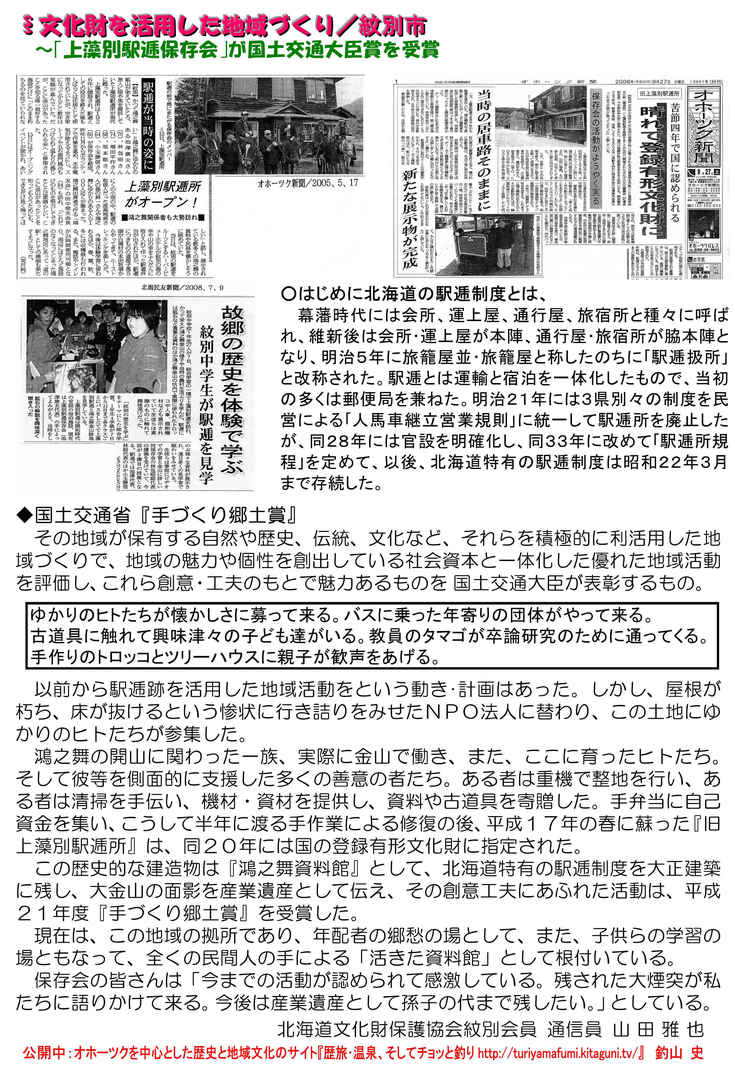

◆国土交通省『手づくり郷土賞』
その地域が保有する自然や歴史、伝統、文化など、それらを積極的に利活用した地域づくりで、地域の魅力や個性を創出している社会資本と一体化した優れた地域活動を評価し、これら創意・工夫のもとで魅力あるものを 国土交通大臣が表彰するもの。 ゆかりのヒトたちが懐かしさに募って来る。バスに乗った年寄りの団体がやって来る。古道具に触れて興味津々の子ども達がいる。教員のタマゴが卒論研究のために通ってくる。手作りのトロッコとツリーハウスに親子が歓声をあげる。以前から駅逓跡を活用した地域活動をという動き・計画はあった。しかし、屋根が朽ち、床が抜けるという惨状に行き詰りをみせたNPO法人に替わり、この土地にゆかりのヒトたちが参集した。鴻之舞の開山に関わった一族、実際に金山で働き、また、ここに育ったヒトたち。そして彼等を側面的に支援した多くの善意の者たち。ある者は重機で整地を行い、ある者は清掃を手伝い、機材・資材を提供し、資料や古道具を寄贈した。手弁当に自己資金を集い、こうして半年に渡る手作業による修復の後、平成17年の春に蘇った『旧上藻別駅逓所』は、同20年には国の登録有形文化財に指定された。この歴史的な建造物は『鴻之舞資料館』として、北海道特有の駅逓制度を大正建築に残し、大金山の面影を産業遺産として伝え、その創意工夫にあふれた活動は、平成21年度『手づくり郷土賞』を受賞した。現在は、この地域の拠所であり、年配者の郷愁の場として、また、子供らの学習の場ともなって、全くの民間人の手による「活きた資料館」として根付いている。保存会の皆さんは「今までの活動が認められて感激している。残された大煙突が私たちに語りかけて来る。今後は産業遺産として孫子の代まで残したい。」としている。北海道文化財保護協会紋別会員 通信員 山田雅也
平成22年度、通常総会と文化財めぐり
~平成22年6月5日(土)
11:00~12:00 通常総会かでる2・7ビル、10F
13:30~16:50 文化財めぐり
○北大古河講堂、農学部本館 、総合博物館ほか
(バスで、移動)
○ サッポロビール博物館等
17:00~19:00 情報交換会(懇親会)
○サッポロビール園
~子ども達へ伝えたい「北海道の歴史と文化」
もっと知ろう、残そう郷土の歴史語り
北海道文化財保護協会
(Tel&Fax 011-271-4220/Mail Address:bunho@abelia.ocn.ne.jp)へ入ろう
第182号 上藻別駅逓保存会が手作り郷土賞 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
情報交換会資料1/2~地域活動の実践
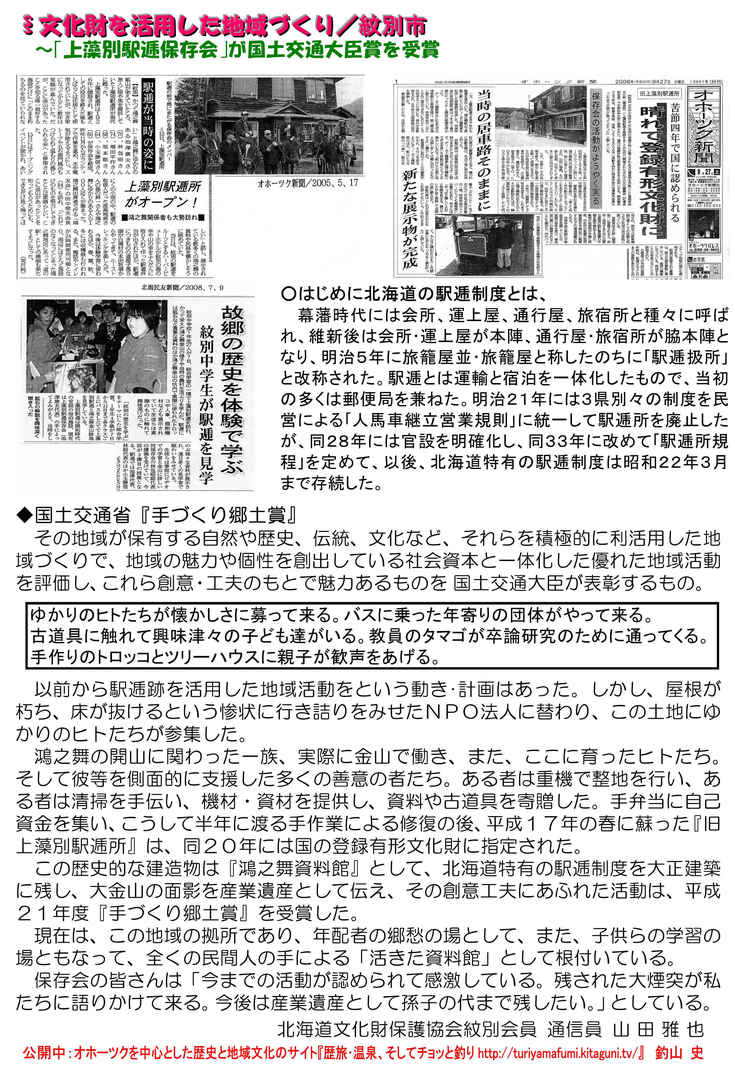

◆国土交通省『手づくり郷土賞』
その地域が保有する自然や歴史、伝統、文化など、それらを積極的に利活用した地域づくりで、地域の魅力や個性を創出している社会資本と一体化した優れた地域活動を評価し、これら創意・工夫のもとで魅力あるものを 国土交通大臣が表彰するもの。 ゆかりのヒトたちが懐かしさに募って来る。バスに乗った年寄りの団体がやって来る。古道具に触れて興味津々の子ども達がいる。教員のタマゴが卒論研究のために通ってくる。手作りのトロッコとツリーハウスに親子が歓声をあげる。以前から駅逓跡を活用した地域活動をという動き・計画はあった。しかし、屋根が朽ち、床が抜けるという惨状に行き詰りをみせたNPO法人に替わり、この土地にゆかりのヒトたちが参集した。鴻之舞の開山に関わった一族、実際に金山で働き、また、ここに育ったヒトたち。そして彼等を側面的に支援した多くの善意の者たち。ある者は重機で整地を行い、ある者は清掃を手伝い、機材・資材を提供し、資料や古道具を寄贈した。手弁当に自己資金を集い、こうして半年に渡る手作業による修復の後、平成17年の春に蘇った『旧上藻別駅逓所』は、同20年には国の登録有形文化財に指定された。この歴史的な建造物は『鴻之舞資料館』として、北海道特有の駅逓制度を大正建築に残し、大金山の面影を産業遺産として伝え、その創意工夫にあふれた活動は、平成21年度『手づくり郷土賞』を受賞した。現在は、この地域の拠所であり、年配者の郷愁の場として、また、子供らの学習の場ともなって、全くの民間人の手による「活きた資料館」として根付いている。保存会の皆さんは「今までの活動が認められて感激している。残された大煙突が私たちに語りかけて来る。今後は産業遺産として孫子の代まで残したい。」としている。北海道文化財保護協会紋別会員 通信員 山田雅也
2010年05月25日
手づくり郷土賞
詳しく解説しています。次号へ校正、転載。
第181号 鴻之舞資料館が手作り郷土賞 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
第181号 鴻之舞資料館が手作り郷土賞 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2010年05月21日
ホタテあれこれ

もんべつの「ホタテ」!! 北海道を代表とする北海道らしい魚介類としては、古くは「三魚」と云われたサケ、マス、ニシンや「俵もの」と呼ばれる中国向けのいりこ、干あわび、コンブなどがあり、北海道の特産品であるホタテ貝も、幕末には干貝柱として登場し、明治に入って同じく盛んに中国へ輸出されて、現在に至っています。 蝦夷地を北海道と名付けたことで知られる松浦武四郎が、幕末に寿都のアイヌ人の民話として『たくさんの海扇(ほたて)が、フタを帆にしてやって来た』と記しており、箱館奉行所の栗本鋤雲は、『蝦夷の三絶』のひとつとしてホタテの干貝柱をあげています。 また、ペリーが箱館に来航したとき、珍しいとホタテの貝殻をアメリカに持ち帰って、後の1857年にはJohn.C.Jayにより、学名 Patinopecten yessoensisと命名されています。Yessoensisとは「蝦夷」のことで、蝦夷櫛皿貝=北海道の櫛のような貝の皿を意味します。 このホタテ漁は北海道でも、とりわけオホーツク海沿岸の中西部が有名で、ホタテ漁の専用漁具と云えば『紋別八尺』と云われるくらいで、また、当地が干貝柱の共販制の先駆けとしても知られるように、「ホタテ漁業史」にとって重要な位置にあります。
第180号 紋別のホタテの歴史(再) 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2010年05月19日
渚滑の大平公園
ようやくオホーツクに春
~昔なつかしい公園に桜
天候がすぐれない日がつづき、晴れてもなかなか気温が上がらなかったオホーツク地方も、ようやく滝上の芝ザクラ、上湧別のチューリップが開花し、当紋別市街の桜も咲き始めた。
さて、ここでは年配者にはなつかしい大平公園の名残り桜を紹介する。
荒れ果てた公園 老木が咲く 池の跡



鴻之舞から移設された住友の社宅

第179号 忘れ去られた公園 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
~昔なつかしい公園に桜
天候がすぐれない日がつづき、晴れてもなかなか気温が上がらなかったオホーツク地方も、ようやく滝上の芝ザクラ、上湧別のチューリップが開花し、当紋別市街の桜も咲き始めた。
さて、ここでは年配者にはなつかしい大平公園の名残り桜を紹介する。
荒れ果てた公園 老木が咲く 池の跡



鴻之舞から移設された住友の社宅

第179号 忘れ去られた公園 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2010年05月16日
釧路・なつかし館が復活
盗難から復活!! 洲崎町なつかし館『蔵』
~市民手作りの私設資料館
釧路市の中野吉次さんが長年に渡って収集したコレクション、明治から昭和にかけての民具や看板など、約3万点を集めた市民手作りの資料館が盗難にあった。中野館長が、冬期休館中の2月18日に蔵へ点検に入ったところ、収蔵品の昭和初期のアイロンや蓄音機などが大量に盗まれていたと云う。
今シーズンの開館が心配されたが、「空き巣被害で、歴史の灯火を消したくない」と、市民団体「洲崎町なつかし館『蔵』を再生させる会」(高橋忠一会長)が、荒らされた蔵を整理し、痛んだ外壁も真っ白に塗り直して、この5月9日のオープンにこぎつけた。
なつかし館は、中野館長が友人と平成元年から開設していた「木材町なつかし館」を、大正4年に建築された現在地の蔵へ移転して、あらためて平成16年にオープンしたもので、以前に私の目を引いた太平洋炭鉱の広告、ケロヨン・サトコちゃんや時代物ものの乳母車は、大丈夫だったのだろうか。



第178号 がんばれ私設資料館 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
~市民手作りの私設資料館
釧路市の中野吉次さんが長年に渡って収集したコレクション、明治から昭和にかけての民具や看板など、約3万点を集めた市民手作りの資料館が盗難にあった。中野館長が、冬期休館中の2月18日に蔵へ点検に入ったところ、収蔵品の昭和初期のアイロンや蓄音機などが大量に盗まれていたと云う。
今シーズンの開館が心配されたが、「空き巣被害で、歴史の灯火を消したくない」と、市民団体「洲崎町なつかし館『蔵』を再生させる会」(高橋忠一会長)が、荒らされた蔵を整理し、痛んだ外壁も真っ白に塗り直して、この5月9日のオープンにこぎつけた。
なつかし館は、中野館長が友人と平成元年から開設していた「木材町なつかし館」を、大正4年に建築された現在地の蔵へ移転して、あらためて平成16年にオープンしたもので、以前に私の目を引いた太平洋炭鉱の広告、ケロヨン・サトコちゃんや時代物ものの乳母車は、大丈夫だったのだろうか。



第178号 がんばれ私設資料館 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2010年05月12日
鶴居村の奉安殿
さらに続く奉安殿の探索
~大型連休の旅 2/6



ヤチ坊主の湿地帯
◆鶴居村の奉安殿
~茂雪裡集落のはずれにたたずむ、旧茂雪裡小学校のものと思われる奉安殿。一時はお社として利用されたらしいが、中には昭和32・3年ごろの額が残されており、そのまま、放置されて痛みは著しい。ヤチ坊主に囲まれた広漠さが、いっそうの郷愁を誘う。入母屋造りの和風を取り入れた和洋折衷、昭和初期のコンクリート建築の特徴を残す。道々1093号沿い。
◆鶴居村軽便鉄道
~旧資料館に展示される廃線時に使用していた機関車と客車
・ディーゼル機関車/泰和車輛工業6t
・自走客車60人乗り/泰和車輛工業8t
昭和2年 馬力による殖民軌道の敷設が着工。
同年3年 新富士~中雪裡、下幌呂~上幌呂間が開通。
同18年 上幌呂~新幌呂間が延長。
同28年 村営となる。
同43年 全線廃止。

第177号 鶴居村の歴史旅 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
~大型連休の旅 2/6



ヤチ坊主の湿地帯

◆鶴居村の奉安殿
~茂雪裡集落のはずれにたたずむ、旧茂雪裡小学校のものと思われる奉安殿。一時はお社として利用されたらしいが、中には昭和32・3年ごろの額が残されており、そのまま、放置されて痛みは著しい。ヤチ坊主に囲まれた広漠さが、いっそうの郷愁を誘う。入母屋造りの和風を取り入れた和洋折衷、昭和初期のコンクリート建築の特徴を残す。道々1093号沿い。
◆鶴居村軽便鉄道
~旧資料館に展示される廃線時に使用していた機関車と客車
・ディーゼル機関車/泰和車輛工業6t
・自走客車60人乗り/泰和車輛工業8t
昭和2年 馬力による殖民軌道の敷設が着工。
同年3年 新富士~中雪裡、下幌呂~上幌呂間が開通。
同18年 上幌呂~新幌呂間が延長。
同28年 村営となる。
同43年 全線廃止。

第177号 鶴居村の歴史旅 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2010年05月08日
消えゆく霧笛(再)
夜霧にむせび鳴く~さようなら浜の風物詩(校正)
本道の霧笛、131年に幕
~霧笛の歴史
濃霧などで視界が利かないときに「ぼー、ぼうー」と鳴った海の道標が国内から消えた。音によって航路を示す霧笛は正式には航路標識「霧信号」と云い、3月31日に根室の納沙布岬、落石岬、花咲港と小樽の日和山を含む国内に残っていた最後の5カ所が全廃された。この3月19日には釧路港、浜中町湯沸岬、広尾町十勝港が、翌20日は厚岸町大黒島厚岸が同じく廃止されていた。
霧笛は昭和43年をピークに全国で53カ所があり、道内では遠洋や沖合い漁業が盛んであった稚内や室蘭、紋別などに計28カ所があった。
我国での音信号の始まりは、明治10年に鐘を叩いて鳴らす「霧鐘」が青森県の尻屋埼灯台に設置され、同12年12月20日(霧笛記念日)には霧笛となった。北海道では、同じく「霧鐘」が同11年に納沙布岬に設けられ、また、その後に火薬による爆発信号機が福山(松前)ほかに設置されたりもした。
最近話題となった釧路では、大正11に行啓した摂政宮殿下(のちの昭和天皇)が濃霧に際し、「霧笛信号はありますか?」とお訊ねになったことから、同14年には釧路埼灯台に最初の霧笛が設置されたが、後に交代して2つめが設けられて、大正の霧笛は釧路市立博物館に保存されている。
釧路では、昨年の11月に「釧路霧笛保存会」が結成され、入会案内のパンフレットを作成して参加を呼び掛けており、「学ぶ・伝える・聞く・保守管理」を基本に講演会や紙芝居など、『海の日や霧フェスなどのイベントと連動して、音を聞く場も提供したい』としている。
~霧笛在りし日の紋別港
さて、そう言えば、当地の紋別港にあった霧笛の開廃止は、いったい何時であったのか?
悲願であった築港が竣工したのが昭和6年、これに併せて北防波堤に紅白色の灯台が設けられたが、同29年には改修されて、赤色灯の通称赤灯台となった。
戦後の遠洋漁業が再開され、地元船ばかりではなく入会の沖合い底引き船で賑わいを見せ始めていた頃で、翌30年10月1日には、紋別市によってモーターサイレン式5馬力の霧笛が、北防波堤灯台に付設され、翌年には海上保安部へと移管されて、後の同56年には船揚げ場付近へ移転された。
GPSなど船舶機器の性能の向上もあり、航路標識としての役割は薄れ、霧笛の老朽化もあって、惜しまれつつも「紋別港北副防波堤霧信号所」は、平成10年9月1日をもって廃止され、翌年には撤去された。
廃止時の霧笛/北海道新聞 初代設置が間もない頃/昭和31年紋別市勢要覧


第176号 むせぶ夜霧に鳴く霧笛
本道の霧笛、131年に幕
~霧笛の歴史
濃霧などで視界が利かないときに「ぼー、ぼうー」と鳴った海の道標が国内から消えた。音によって航路を示す霧笛は正式には航路標識「霧信号」と云い、3月31日に根室の納沙布岬、落石岬、花咲港と小樽の日和山を含む国内に残っていた最後の5カ所が全廃された。この3月19日には釧路港、浜中町湯沸岬、広尾町十勝港が、翌20日は厚岸町大黒島厚岸が同じく廃止されていた。
霧笛は昭和43年をピークに全国で53カ所があり、道内では遠洋や沖合い漁業が盛んであった稚内や室蘭、紋別などに計28カ所があった。
我国での音信号の始まりは、明治10年に鐘を叩いて鳴らす「霧鐘」が青森県の尻屋埼灯台に設置され、同12年12月20日(霧笛記念日)には霧笛となった。北海道では、同じく「霧鐘」が同11年に納沙布岬に設けられ、また、その後に火薬による爆発信号機が福山(松前)ほかに設置されたりもした。
最近話題となった釧路では、大正11に行啓した摂政宮殿下(のちの昭和天皇)が濃霧に際し、「霧笛信号はありますか?」とお訊ねになったことから、同14年には釧路埼灯台に最初の霧笛が設置されたが、後に交代して2つめが設けられて、大正の霧笛は釧路市立博物館に保存されている。
釧路では、昨年の11月に「釧路霧笛保存会」が結成され、入会案内のパンフレットを作成して参加を呼び掛けており、「学ぶ・伝える・聞く・保守管理」を基本に講演会や紙芝居など、『海の日や霧フェスなどのイベントと連動して、音を聞く場も提供したい』としている。
~霧笛在りし日の紋別港
さて、そう言えば、当地の紋別港にあった霧笛の開廃止は、いったい何時であったのか?
悲願であった築港が竣工したのが昭和6年、これに併せて北防波堤に紅白色の灯台が設けられたが、同29年には改修されて、赤色灯の通称赤灯台となった。
戦後の遠洋漁業が再開され、地元船ばかりではなく入会の沖合い底引き船で賑わいを見せ始めていた頃で、翌30年10月1日には、紋別市によってモーターサイレン式5馬力の霧笛が、北防波堤灯台に付設され、翌年には海上保安部へと移管されて、後の同56年には船揚げ場付近へ移転された。
GPSなど船舶機器の性能の向上もあり、航路標識としての役割は薄れ、霧笛の老朽化もあって、惜しまれつつも「紋別港北副防波堤霧信号所」は、平成10年9月1日をもって廃止され、翌年には撤去された。
廃止時の霧笛/北海道新聞 初代設置が間もない頃/昭和31年紋別市勢要覧


第176号 むせぶ夜霧に鳴く霧笛
2010年05月04日
弟子屈の奉安殿
どんどん続く、奉安殿の探索
~大型連休の旅 1/6
 弟子屈町の奉安殿 2010年3月~5月調査 協力:弟子屈町教育委員会 北海道文化財保護協会 釣山 史 昨年(平成21年)、惜しくも屈斜路湖畔の和琴神社として利用されていた1棟が、老朽化のために取り壊されたが、それでも道東の弟子屈町には、現在でも3棟の奉安殿が現存する。昭和に入ってからの奉安殿の多くが、コンクリート造りであるのに対し、弟子屈町の奉安殿は、いづれも木造であり、奉安殿が現存する集落の高齢者が「奉安殿はどれも似たもの」と証言するように、この3棟は、造りがたいへんよく似ている。中心校にあったものを模倣したのか、あるいは施行業者が同じであったか、切妻造り平入りの破風に施された細工と配置される旭日の特徴が一致している。てしかがの蔵(資料館) もともと仁多地区にあったものを、市街地の資料館へ移転して展示したもので、その時に彩色が施された。この資料館には、教育勅語謄本もあるという。仁多地区 ちょうど交換されたかのように、市街にあった奉安殿は、郊外仁多地区の国道243号沿いに移転された。現在は、地区のお社として利用されている。旧札友内小学校跡地 奉安殿は、戦後も移転されずに学校敷地内にあったといい、たぶん内部を改修されて、倉庫として利用されたのだろう。その後の学校の建て直しに際し、若干、移動して国道243号沿いの現在地に至る。
弟子屈町の奉安殿 2010年3月~5月調査 協力:弟子屈町教育委員会 北海道文化財保護協会 釣山 史 昨年(平成21年)、惜しくも屈斜路湖畔の和琴神社として利用されていた1棟が、老朽化のために取り壊されたが、それでも道東の弟子屈町には、現在でも3棟の奉安殿が現存する。昭和に入ってからの奉安殿の多くが、コンクリート造りであるのに対し、弟子屈町の奉安殿は、いづれも木造であり、奉安殿が現存する集落の高齢者が「奉安殿はどれも似たもの」と証言するように、この3棟は、造りがたいへんよく似ている。中心校にあったものを模倣したのか、あるいは施行業者が同じであったか、切妻造り平入りの破風に施された細工と配置される旭日の特徴が一致している。てしかがの蔵(資料館) もともと仁多地区にあったものを、市街地の資料館へ移転して展示したもので、その時に彩色が施された。この資料館には、教育勅語謄本もあるという。仁多地区 ちょうど交換されたかのように、市街にあった奉安殿は、郊外仁多地区の国道243号沿いに移転された。現在は、地区のお社として利用されている。旧札友内小学校跡地 奉安殿は、戦後も移転されずに学校敷地内にあったといい、たぶん内部を改修されて、倉庫として利用されたのだろう。その後の学校の建て直しに際し、若干、移動して国道243号沿いの現在地に至る。
第175号 弟子屈町の現存する奉安殿 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
~大型連休の旅 1/6
 弟子屈町の奉安殿 2010年3月~5月調査 協力:弟子屈町教育委員会 北海道文化財保護協会 釣山 史 昨年(平成21年)、惜しくも屈斜路湖畔の和琴神社として利用されていた1棟が、老朽化のために取り壊されたが、それでも道東の弟子屈町には、現在でも3棟の奉安殿が現存する。昭和に入ってからの奉安殿の多くが、コンクリート造りであるのに対し、弟子屈町の奉安殿は、いづれも木造であり、奉安殿が現存する集落の高齢者が「奉安殿はどれも似たもの」と証言するように、この3棟は、造りがたいへんよく似ている。中心校にあったものを模倣したのか、あるいは施行業者が同じであったか、切妻造り平入りの破風に施された細工と配置される旭日の特徴が一致している。てしかがの蔵(資料館) もともと仁多地区にあったものを、市街地の資料館へ移転して展示したもので、その時に彩色が施された。この資料館には、教育勅語謄本もあるという。仁多地区 ちょうど交換されたかのように、市街にあった奉安殿は、郊外仁多地区の国道243号沿いに移転された。現在は、地区のお社として利用されている。旧札友内小学校跡地 奉安殿は、戦後も移転されずに学校敷地内にあったといい、たぶん内部を改修されて、倉庫として利用されたのだろう。その後の学校の建て直しに際し、若干、移動して国道243号沿いの現在地に至る。
弟子屈町の奉安殿 2010年3月~5月調査 協力:弟子屈町教育委員会 北海道文化財保護協会 釣山 史 昨年(平成21年)、惜しくも屈斜路湖畔の和琴神社として利用されていた1棟が、老朽化のために取り壊されたが、それでも道東の弟子屈町には、現在でも3棟の奉安殿が現存する。昭和に入ってからの奉安殿の多くが、コンクリート造りであるのに対し、弟子屈町の奉安殿は、いづれも木造であり、奉安殿が現存する集落の高齢者が「奉安殿はどれも似たもの」と証言するように、この3棟は、造りがたいへんよく似ている。中心校にあったものを模倣したのか、あるいは施行業者が同じであったか、切妻造り平入りの破風に施された細工と配置される旭日の特徴が一致している。てしかがの蔵(資料館) もともと仁多地区にあったものを、市街地の資料館へ移転して展示したもので、その時に彩色が施された。この資料館には、教育勅語謄本もあるという。仁多地区 ちょうど交換されたかのように、市街にあった奉安殿は、郊外仁多地区の国道243号沿いに移転された。現在は、地区のお社として利用されている。旧札友内小学校跡地 奉安殿は、戦後も移転されずに学校敷地内にあったといい、たぶん内部を改修されて、倉庫として利用されたのだろう。その後の学校の建て直しに際し、若干、移動して国道243号沿いの現在地に至る。第175号 弟子屈町の現存する奉安殿 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/



