2012年03月22日
北洋操業と霧笛のお話し(改)

◆遠洋・沖底が華やかな頃のお話し
~非常に危険だった昔の北洋操業
戦後に日本の遠洋漁業が解禁されたのは昭和27年で、紋別では同30年、31年には北洋カムチャッカ海域のサケ・マス漁業船団の中継基地となり、また、同じく同30年からは「日米水産」と「極洋捕鯨」のタラ延縄漁船の根拠地ともなった。そして旧ソ連のベーリング海域などでの底曳試験操業が開始されたのが昭和32年である。
遠洋・沖底漁業が華やかしい頃、濃霧などで視界が利かないときに「ぼー、ぼうー」と鳴った港町の風物詩は何処へ行ったか?
悲願であった紋別築港が竣工したのが昭和6年、これに併せて北防波堤に紅白色の灯台が設けられた。築港以前には、今の造船所のあたりには岩礁と浅瀬があり、そこには一本松が建てられて、松印と呼ばれて航行の目印となっていたと云う。
昭和29年には北防波堤灯台が改修されて赤色灯の通称赤灯台となり、翌30年10月1日には、紋別市によってモーターサイレン式5馬力の霧笛が、灯台に付設され、さらに翌年には海上保安部へと移管された。
さて、当時、弁天町にあった松田水産所属の『丸高丸・177㌧、17人乗り』は、昭和34年3月6日9時頃、僚船へ『天気すこぶる晴朗で波静か、順調な航行を続けている』との通信を最後に消息を絶った。「丸高丸」は前年に進水したばかりの新造の北洋底曳試験船だった。
その後に遺留品などの手がかりも全くなく、行方不明から四十九日が経った4月26日には報恩寺において小笠原俊英船長、高橋亮一漁労長ほか乗組員の合同慰霊祭がしめやかに執り行われた。
この前月には大洋漁業の「第十七明石丸・73㌧、15人乗り、鍋谷精司船長」がカムチャッカ南端のブレスブ沖で沈没しており、「丸高丸」は皮肉にも1年前にはカムチャッカ沖で遭難したタラ延縄漁船「第十二大黒丸・132㌧、18人乗り、阿部喜一船長」の最後の無線を受け取った僚船であり、また、この昭和34年には当地へ巡視船「そらち」が配備されたのであった。
第298回 遠洋漁業、沖合底曳漁業が再開した頃 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2012年03月18日
ブラキストン、オホーツクを探検
◆紋別にも来たブラキストン(改)
 さて、意外と知られていないのは、鳥類の研究で有名な、あのブラキストンが明治二年に道東北を巡り、詳細な紀行文を残しているということ。ブラキストンは、新政府から宗谷で難破した英国艦の調査を依頼されて所有船あきんど号で函館を出港、道東の浜中に上陸すると、そこから海岸沿いに宗谷へ至った。
さて、意外と知られていないのは、鳥類の研究で有名な、あのブラキストンが明治二年に道東北を巡り、詳細な紀行文を残しているということ。ブラキストンは、新政府から宗谷で難破した英国艦の調査を依頼されて所有船あきんど号で函館を出港、道東の浜中に上陸すると、そこから海岸沿いに宗谷へ至った。
こうして途中の紋別を通過、彼の記録では当時の紋別場所について、『岩礁が風波を多少防ぐ程度の少し引っ込んだ湾とは言えないくらいのもので、漁場には大きな住宅と役所が1軒づつ、それをアイヌ人の小屋が取り囲んでおり、この時は和船一艘が沖泊めされていた。』とあり、番屋の差配人と船長の話しでは、『オホーツク沿岸は、冬には沖合い3~4里は凍るけれども、宗谷海峡は、日本海からの暖流による海流の速さと暖かさで凍らず、あの大量の氷は、樺太沿岸で結氷したものが、冬の北風によって流れ来るもの…、斜里と紋別の経営は採算が取れないが、他に非常に利益のある標津場所があり、どこか一カ所を放棄すると全てを召し上げられてしまう(山田寿兵衛の請負)。』と聞き取りしている。
このときの船長は、外国船での経験があり、また、案内人のアイヌの青年は、ヒゲをそり、日本風の髪形をしてカナ文字を書いたとしている。
第297回 ブラキストンの話し(再) 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
 さて、意外と知られていないのは、鳥類の研究で有名な、あのブラキストンが明治二年に道東北を巡り、詳細な紀行文を残しているということ。ブラキストンは、新政府から宗谷で難破した英国艦の調査を依頼されて所有船あきんど号で函館を出港、道東の浜中に上陸すると、そこから海岸沿いに宗谷へ至った。
さて、意外と知られていないのは、鳥類の研究で有名な、あのブラキストンが明治二年に道東北を巡り、詳細な紀行文を残しているということ。ブラキストンは、新政府から宗谷で難破した英国艦の調査を依頼されて所有船あきんど号で函館を出港、道東の浜中に上陸すると、そこから海岸沿いに宗谷へ至った。こうして途中の紋別を通過、彼の記録では当時の紋別場所について、『岩礁が風波を多少防ぐ程度の少し引っ込んだ湾とは言えないくらいのもので、漁場には大きな住宅と役所が1軒づつ、それをアイヌ人の小屋が取り囲んでおり、この時は和船一艘が沖泊めされていた。』とあり、番屋の差配人と船長の話しでは、『オホーツク沿岸は、冬には沖合い3~4里は凍るけれども、宗谷海峡は、日本海からの暖流による海流の速さと暖かさで凍らず、あの大量の氷は、樺太沿岸で結氷したものが、冬の北風によって流れ来るもの…、斜里と紋別の経営は採算が取れないが、他に非常に利益のある標津場所があり、どこか一カ所を放棄すると全てを召し上げられてしまう(山田寿兵衛の請負)。』と聞き取りしている。
このときの船長は、外国船での経験があり、また、案内人のアイヌの青年は、ヒゲをそり、日本風の髪形をしてカナ文字を書いたとしている。
第297回 ブラキストンの話し(再) 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2012年03月15日
ホタテの2番汁
 ◆ホタテエキスの濃縮技術は紋別地方から(改)
◆ホタテエキスの濃縮技術は紋別地方から(改)さて、カキの効能は古くから知られていて『ひとつぶ300メートル』のCMは有名だ。大正8年に江崎利一はカキエキスからグリコーゲンを抽出し、同10年に『栄養菓子グリコ』として創業を開始した。
同じく栄養価の高いホタテをどうにか活用できないか?。北海道水産試験場稚内支場は、昭和9年のエリザ・クラブ商会頓別工場での予備試験をかわきりに、従来、廃棄されていた乾貝柱の製造工程で発生する二番煮汁から、グリコーゲンを抽出するための製造試験を開始した。
昭和10年は、北海道漁業缶詰㈱紋別工場において、
①煮汁腐敗防止の試験
②製造法の試験
③グリコーゲン含有量簡易鑑別法の試験
④調味料に関する試験
を行い、このときの真空蒸留濃縮法は、現在へと受け継がれている。
つづいて昭和11には、湧別の北洋水産工業㈱で製造したサンプルを薬品会社数社に発送して協力を仰いだ。
間もなく既製の真空蒸発鍋が開発されたこともあり、ホタテエキスの濃縮事業が各地で行われるようになって、紋別では昭和11年に創業の昭和産業㈱が「帆立貝煮汁濃縮液」として販売している。
これらの多くは主に栄養剤とされ、また、調味料にも利用されたが、昭和10年頃の北見物産協会のパンフレットに北見のお土産として、常呂と紋別の「帆立センベイ」をあげており、ひょっとしてホタテエキスを使っていたのかも知れない。
第296回 ほたてエキス 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2012年03月04日
イモ版・香川

予告:釣山コレクション、香川軍男の原点 昨年度は、以前より行ってみたいと思っていた「野付通行屋遺跡」を訪問、自費制作による絵葉書を作成し、また、長年、やりたかった地元に関係する南極講演が開催できた。 さて、ことしの目標であるが、北海道文化財保護協会で、紋別市の旧鴻之舞金山を巡見しようとの案が持ち上がり、実現されることを心待ちに準備を進めている。そうしてもうひとつは、当地で育った北海道を代表する版画家・香川軍男展の開催である。 彼は果敢な少年期を当地で過ごしたもので、それを知った数年前から着々と準備を進めていたもので、ちょっとした展覧会に耐えうる程度の作品は取り揃えた。数十点はあろうか、デッサン、燐票?(蔵書票代わりであろう) 、手作りの私家本、そして香川の原点である薯版年賀状に、『いもほりの記』自筆原稿ほかの数々で、中には発行番号の無いサイン本があり、贈呈されたものであろう。 秋から年末の間をめざしたい。 香川は『いも版AINU帖』あとがきで、 過去茫々、尋常小学校のとき、コタンからかよっているともだちの持っていた、文様を焼き火箸でつけたガッケ(竹を割ってつくった遊び道具)が欲しかった。ほんとうにいいものだった。彼はどうしているだろうか。 …と語っている。
第295回 イモ版・香川軍男 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/
2012年03月01日
歴旅・別海大好き
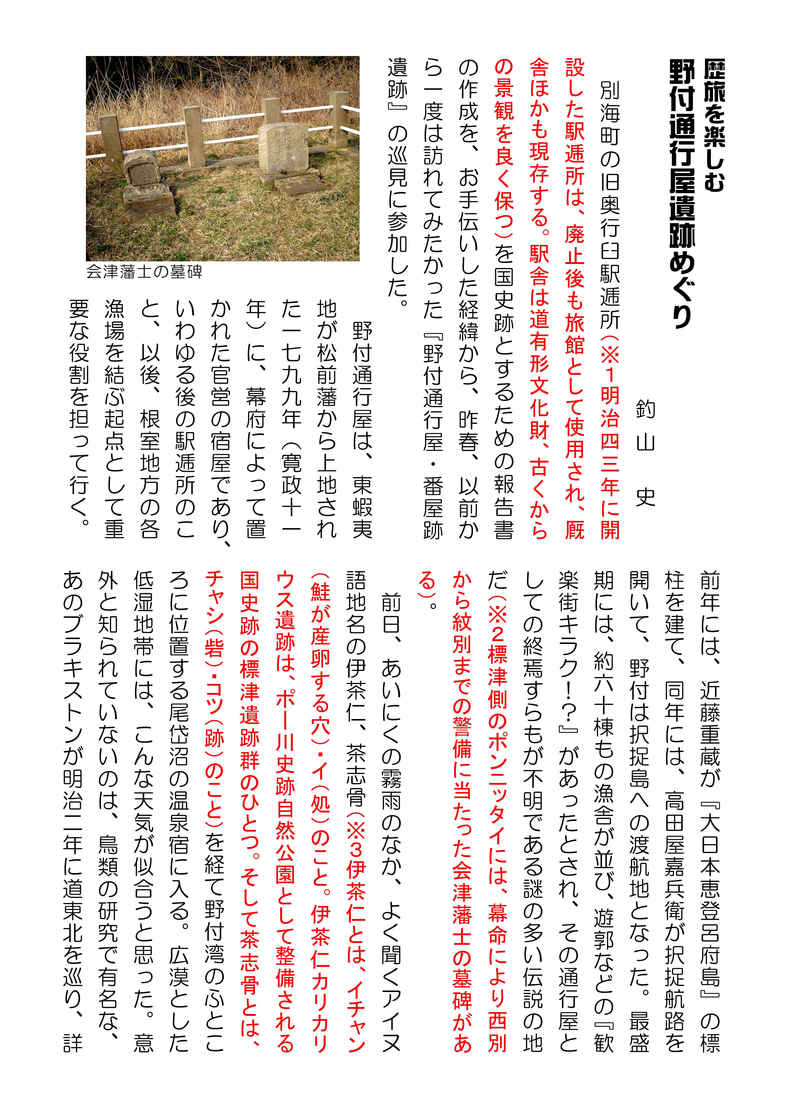


歴旅を楽しむ 野付通行屋遺跡めぐり 釣山史 別海町の旧奥行臼駅逓所(※1明治四三年に開設した駅逓所は、廃止後も旅館として使用され、厩舎ほかも現存する。駅舎は道有形文化財、古くからの景観を良く保つ)を国史跡とするための報告書の作成を、お手伝いした経緯から、昨春、以前から一度は訪れてみたかった『野付通行屋・番屋跡遺跡』の巡見に参加した。 野付通行屋は、東蝦夷地が松前藩から上地された一七九九年(寛政十一年)に、幕府によって置かれた官営の宿屋であり、いわゆる後の駅逓所のこと、以後、根室地方の各漁場を結ぶ起点として重要な役割を担って行く。前年には、近藤重蔵が『大日本恵登呂府島』の標柱を建て、同年には、高田屋嘉兵衛が択捉航路を開いて、野付は択捉島への渡航地となった。最盛期には、約六十棟もの漁舎が並び、遊郭などの『歓楽街キラク!?』があったとされ、その通行屋としての終焉すらもが不明である謎の多い伝説の地だ(※2標津側のポンニッタイには、幕命により西別から紋別までの警備に当たった会津藩士の墓碑がある)。 前日、あいにくの霧雨のなか、よく聞くアイヌ語地名の伊茶仁、茶志骨(※3伊茶仁とは、イチャン(鮭が産卵する穴)・イ(処)のこと。伊茶仁カリカリウス遺跡は、ポー川史跡自然公園として整備される国史跡の標津遺跡群のひとつ。そして茶志骨とは、チャシ(砦)・コツ(跡)のこと)を経て野付湾のふところに位置する尾岱沼の温泉宿に入る。広漠とした低湿地帯には、こんな天気が似合うと思った。意外と知られていないのは、鳥類の研究で有名な、あのブラキストンが明治二年に道東北を巡り、詳細な紀行文を残しているということ。野付では、ツルやオジロワシについて触れている(※4ブラキストンは、新政府から宗谷で難破した英国艦の調査を依頼されて函館を出港、道東の浜中に上陸すると、そこから海岸沿いに宗谷へ至った。ツルは、特別天然記念物のタンチョウと思われ、また、オジロワシも天然記念物)。約百四十年前に、ブラキストンが通ったであろう路である。温泉は、塩泉の温度が高くやわらかく、思いのほかイイ湯であった。知ってはいたが、名物のゴソガレイの「姿作り」に一瞬たじろぐ。 翌朝、みぞれ・強風のなか、野付半島ネイチャーセンターへ向かう。自然を愛する歴男・歴女、約二十人が集合した。巡見前に石渡学芸員の概要説明を聞く。石渡氏は、地元に残る寛政年間から明治初頭にかけての加賀家文書(※5江戸時代の末期に根室地方のアイヌ語通訳として活躍した加賀一族が残した古文書)を研究しており、本日の先導役だ。 さて、センターから数台の車に分乗し、龍神崎を経て、日ごろは一般車両が進入禁止の砂利道に侵入、通行屋跡までは、片道二km強を歩くことになる。途中、日常では見られない野鳥に出会う。そうして枯野にある大きな窪みは漁舎の跡だ。 さらに砂泥に足を取られながら干潟を行くと、わずかに土塁の痕跡が見て取れた。ここが通行屋の跡だという。以前にも訪れたことがある同道のご婦人によると、この二~三年で明らかに浸食が進んでいるという。もはや干潮のときにしかたどれない状況にある。 この蝦夷地の最奥に残る貴重な遺跡も、あと数年で完全に海中へ没してしまうだろう。平成十五年から十七年にかけては、喫緊の発掘調査が行われ、遺物の一部が資料館に収蔵された(※6収蔵品の中の面白いものに、幕末の箱館で鋳造されたが、全くの不評で短命に終わった『箱館通宝』があり、それでも最奥の根室地方にまで通用していたことが分かる)。 やや高い奥手には、慰霊塔と数基の墓碑が建っている。周辺に点在する小さな穴ぼこは、未発掘だが墓穴であろうとのこと。はるかな昔、この荒涼とした怪外の遠国に埋もれた魂は、如何に故郷を憶うのだろう。 ここから折り返して、砂州の一番高いところをとぼとぼ戻ると洗濯板のような微かな凹凸を発見、それは客土を施された畑の畝跡だった。ハマナスのトゲとげが体に刺さる、それを左右にかわしながら、腰痛持ちには、なかなか辛い道のりをしばらく進む。もう一基の墓碑を左手に見ながら、駅逓所の報告書をまとめられた戸田学芸員と肩を並べて帰路につく。道すがらの荒野に歴史談義の花が咲いた。 目標物も無く、荒野に溶け込むように点在する遺物、遺跡。ひとりでの探索は不可能と思われ、機会を与えて頂いた石渡氏、戸田氏に感謝々で、楽しい一日、ありがとうございました。 追伸 別海町には、そのほか旧標津線を記念した鉄道記念館や旧奥行臼駅があり、旧軍施設や奉安殿、道指定天然記念物の西別湿原ヤチカンバ群落地など、魅力がいっぱい。ぜひとも皆さんに来訪をおススメしたい。 会津藩士の墓碑 オンネ茶志骨 伊茶仁川 別海町のタンチョウ
第294回 別海町の文化遺産 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/



