2010年08月17日
沖底船と加工業
第199回 沖合底びき網漁船と水産加工業の変遷 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/





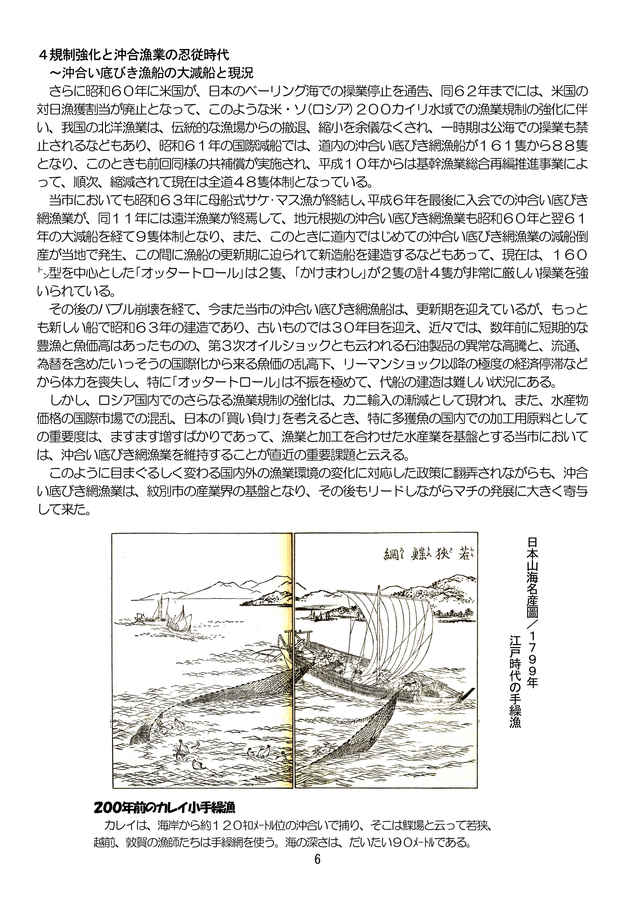 戦前の紋別港 当時、最新鋭だった松田冷蔵庫 戦後、間もない頃の小手繰船 昭和32年頃、出港の景、霧笛 沖底船の水揚げ、春ホッケ、追いニシン 日本山海名産圖/江戸時代の手繰漁、200年前のカレイ小手繰漁 カレイは、海岸から約120キロメートル位の沖合いで捕り、そこは鰈場と云って若狭、越前、敦賀の漁師たちは手繰網を使う。海の深さは、だいたい90メートルである。 紋別を例とした沖合底びき漁船と水産加工の歴史 §1.機船底びき網漁業の興り 1沖合底びき網漁業の勃興 ~動力船の登場 単に「機船」と呼ぶとき、それは「底びき網漁船」のことを示すが、我国における近代的な沖合底びき網漁業は、明治36年に輸入された機船トロールに始まると云う、底びき網漁業は平安末期の1087年の記録『能登浦領内ノ事』に「北ハカレイ引ヲ定也」とあり、若狭湾では、寛文期以前から「沖手繰による鰈引き」が盛んであった。 この若狭湾での明治43年の試験操業は失敗に終わったが、続いて大正2年に島根県で始まった沖手繰は、漸次、成績を上げると四国地方、そして日本海の各地へと広まった。 北海道では、明治38年の室蘭での試験操業が最初と云われ、同41年には8隻の底びき網機船があったとも云う。後年、同漁業の中心地となった小樽では、大正元年に始めて試みられたが、この時には定着しなかった。 後に道内において継続的な経済操業に至ったのは大正の中期以降の小樽や函館であり、大正9年の底びき網機船の登録は、小樽100、岩内10、函館4、室蘭33、釧路52、根室3、宗谷1、留萌12の計215隻であったが、実際の操業は100隻程度だった。 道庁では、この様ににわかに勃興した底びき網機船を、夏枯れに対応した通年操業とするため、大正9年から翌10年にかけてオホーツク海の漁場調査を行い、同12年と14にはトロール試験を実施して、新開の北見漁場へと誘導した。 2紋別でのはじまり ~第三寅丸の回航 紋別では、明治36年頃から無動力の川崎船によるカレイ小手繰が行われていて、大正年間には紋別の一本松から興部の砂留の間で2~3隻が操業していたと云うが、加工・流通の未発達な時代にあっては振るわなかった。 当地での最初の動力船は、紋別漁協が大正3年に導入したホタテ監視船であったが、数年後には、それを高嶋春松が購入して、紋別~湧別間の輸送を行いながらマガレイ漁をはじめたと云い、これが網走管内の底びき網機船の始まりであった。 こうして紋別でも漁業近代化の波が現れ、大正12年には小樽から松田鉄蔵の機船「第三寅丸」が回航してマガレイを大漁し、鮮魚は主に旭川方面へ販売して、あとはカマボコや魚粕などに加工した。また、同年に地元では伴田惣十郎が機船2隻を建造し、翌年には操業を始めた。 3紋別水産界の発展 ~近代的水産業の現れ
戦前の紋別港 当時、最新鋭だった松田冷蔵庫 戦後、間もない頃の小手繰船 昭和32年頃、出港の景、霧笛 沖底船の水揚げ、春ホッケ、追いニシン 日本山海名産圖/江戸時代の手繰漁、200年前のカレイ小手繰漁 カレイは、海岸から約120キロメートル位の沖合いで捕り、そこは鰈場と云って若狭、越前、敦賀の漁師たちは手繰網を使う。海の深さは、だいたい90メートルである。 紋別を例とした沖合底びき漁船と水産加工の歴史 §1.機船底びき網漁業の興り 1沖合底びき網漁業の勃興 ~動力船の登場 単に「機船」と呼ぶとき、それは「底びき網漁船」のことを示すが、我国における近代的な沖合底びき網漁業は、明治36年に輸入された機船トロールに始まると云う、底びき網漁業は平安末期の1087年の記録『能登浦領内ノ事』に「北ハカレイ引ヲ定也」とあり、若狭湾では、寛文期以前から「沖手繰による鰈引き」が盛んであった。 この若狭湾での明治43年の試験操業は失敗に終わったが、続いて大正2年に島根県で始まった沖手繰は、漸次、成績を上げると四国地方、そして日本海の各地へと広まった。 北海道では、明治38年の室蘭での試験操業が最初と云われ、同41年には8隻の底びき網機船があったとも云う。後年、同漁業の中心地となった小樽では、大正元年に始めて試みられたが、この時には定着しなかった。 後に道内において継続的な経済操業に至ったのは大正の中期以降の小樽や函館であり、大正9年の底びき網機船の登録は、小樽100、岩内10、函館4、室蘭33、釧路52、根室3、宗谷1、留萌12の計215隻であったが、実際の操業は100隻程度だった。 道庁では、この様ににわかに勃興した底びき網機船を、夏枯れに対応した通年操業とするため、大正9年から翌10年にかけてオホーツク海の漁場調査を行い、同12年と14にはトロール試験を実施して、新開の北見漁場へと誘導した。 2紋別でのはじまり ~第三寅丸の回航 紋別では、明治36年頃から無動力の川崎船によるカレイ小手繰が行われていて、大正年間には紋別の一本松から興部の砂留の間で2~3隻が操業していたと云うが、加工・流通の未発達な時代にあっては振るわなかった。 当地での最初の動力船は、紋別漁協が大正3年に導入したホタテ監視船であったが、数年後には、それを高嶋春松が購入して、紋別~湧別間の輸送を行いながらマガレイ漁をはじめたと云い、これが網走管内の底びき網機船の始まりであった。 こうして紋別でも漁業近代化の波が現れ、大正12年には小樽から松田鉄蔵の機船「第三寅丸」が回航してマガレイを大漁し、鮮魚は主に旭川方面へ販売して、あとはカマボコや魚粕などに加工した。また、同年に地元では伴田惣十郎が機船2隻を建造し、翌年には操業を始めた。 3紋別水産界の発展 ~近代的水産業の現れ
前述の以降は、夏枯れ対策として小樽・室蘭・留萌からも多くの機船が回航し、紋別を根拠地に常時15・6隻以上が、主に雄武から興部沖の浅いところで35~50㍍、深いところでは60~80㍍の範囲でマガレイを大漁したが、昭和15年頃までの地元の登録船は、松田2、伴田2、浜田・上森・太田が各1の計7隻で一定した。 昭和11年の千島も含めた全漁獲高では、紋別が全道市町村中で第5位にあり、その内のカレイ漁は3位で、底引き網での同漁はダントツの1位であった。 当時は、既に地元の仲買人はいたが(大正4年に紋別魚市場が開設)、大きな取引は主に小樽の問屋衆で占められていて、季節的に大漁されるマガレイなどは、価格が不安定であり、この頃には、底びき網の船主が大きなカレイは自ら東京へ送ったりもしたが、うまく届くと大儲け、途中で腐ると丸損という有り様だった。 この鮮魚の出荷には、その前提となる冷蔵庫が必要であり、すでに大正年間には2つの貯氷庫があり、昭和5年には松田鉄蔵と松崎隆一による全道でも2番目の当時としては最新式の冷蔵庫が建設されたが、築地市場への鮮魚特急と呼ばれた冷蔵貨車は、その台数が限られており、昭和14年に「北海道機船底曳網漁業水産組合紋別支部」が発足し、同じく「紋別機船底曳網漁業出荷組合」を結成して、共同での発送を行った。 これら機船底びき網漁業によるマガレイ漁と、それにかかる冷凍・冷蔵技術の導入など、鮮魚流通に向けた努力は、築地や小田原、札幌などへの地方出荷となり、後の「もんべつマガレイ」ほか、地元海産物の産地ブランドへと繋がって行く。 §2.機船底びき網漁業の転換と戦後の加工業 1底びき網漁業の濫立と停滞 ~沿岸漁業の荒廃 特に北海道では、昭和初期に急激な漁船数の増加を見たが、これは単に底びき網機船の隻数が増えたのであり、漁船自体の大型化は伴わずに密漁が横行し、それは資源の乱獲と沿岸漁業者との紛争を招くことになり、戦時の燃油・資材の不足もあって中型の底びき網機船自身も採算が取れない状況に陥ってしまった。 当地においても、マガレイのほかに昭和2年頃からはアブラザメ漁も始めてはいたが、同8年頃から特にカレイ類の資源減少が現れ、同12年からはタラ、スケソウを漁獲するようになり、これらの加工はサメヒレなどの乾物と一部が練物とされたほかは、主に魚油や魚粕とした。 こうして遂に昭和5年には「機船底曳網漁業取締規則」が改定され、規制の強化が図られることになったが、戦時の食料確保と徴用船への対応から規制は次第に緩慢となり、結局、これらによって漁業制度は崩壊してしまう。
いっぽう、昭和16年からの統制経済は脱仕込ともなり、食糧不足の中で一定の価格が維持されたことから、小規模漁業者の負債は整理され、また、それまで廉価であったホッケが脚光をあびるようになるなどの副産物を生んだ。 しかし、戦後に至って食料不足がいっそう深刻化すると、乱獲による資源の減少は著しいものとなり、また、紋別でも昭和27年を最後にニシンの群来が見られなくなるなど、かえって漁獲効率が高い小手繰船を増加させ、密漁船が横行するという悪循環となってしまった。 2底びき網漁業の戦後処理 ~小中底びき船の整理 小型機船底びき網漁業(小手繰船)は、昭和19年に10㌧未満を限り合法としたが、実際には20㌧前後も黙認され、さらに戦後に千島海域を失った底びき船が入り込んで沿岸資源の減少が深刻となり、沿岸漁業との摩擦が拡大されると、底びき船は、より沖合への出漁を余儀なくされ、沿岸から沖合いへ、沖合いから遠洋へと船の大型化・近代化が図られるようになったが、沖合底びき網漁業の採算は難しく、後にそれは北洋操業へと転換して行く。 昭和23年に、35㌧未満が35㌧へ、35㌧から40㌧未満は40㌧に、そして40㌧から45㌧未満が45㌧への増トンを認めて、実測との補正を行い、同25年には北海道庁が、小手繰船の整理と無許可船の根絶を図るため、小手繰網漁船の許可船4隻に対して1隻の中型底びき網漁船への転換と、無許可船は8隻から1隻の中型底びき網漁船への転換を指導した。 昭和26年における紋別根拠の中型機船底びき網漁業の登録数(入会、2箇所登録有り)は61隻あり、その船籍は紋別(21)、網走(9)、函館(8)、根室(6)、小樽(5)、東京(5)、興部(3)、湧別(3)、雄武(1)とあり、主要な経営主としては、東京の日東水産㈱が6隻、小樽の松田関連の5隻(大成2、辰蔵2、松田漁業1)などがあった。この年には機船底びき網の15㌧未満を小型、それ以上から60㌧までが中型と定められ、のち北海道と東北に限り、木船75㌧、鋼船85㌧までとされた。 3機船漁業の転換 ~漁船の大型化、より沖合いへ 昭和27年にマッカーサーラインが撤廃され、戦後の日本の遠洋漁業が解禁された。昭和29年には『沿岸から沖合いへ、沖合いから遠洋』への政策が固まり、それまで地方で行われていた新開漁場の開発が国の事業となり、ベーリング海域などで遠洋底びき試験操業が開始されて、同30年から紋別へも水揚されるようになると、同32年には紋別船も出漁を開始した。 昭和31年には、これら新開漁場への出漁や他の漁業との兼業など、季節的に沖合底びき網漁業を行わない船の増トンが認められ、このような経緯の中で当地を主な根拠地とする昭和26年の操業船が48隻であったものが、同35年には35隻に減少した一方で、70㌧以上が5隻出現した。昭和36~38年にかけては全道で沖合底びき網漁業を大減船し、一部を北洋底びき網漁業へ転換。紋別では6隻が減船し、うち1隻が転換した(北転船と云う)。 そうして昭和37年からは船員の労働環境の改善を目的とした96㌧型への増トンが図られると、漁船の大型化は急激に進行し、この間、沖合底びき網漁業は、北海道で最も安定した漁業となっていたが、昭和30年代末をピークに漁獲量が下向を示し、同40年代に入って徐々に漁価が低下しだすと、人手不足もあいまって深刻な経営不振に陥ってしまった。紋別でも昭和43年の着業者は21事業者、24隻となっていた。 こうした状況下で打開策とされたのが『124㌧型船』への移行と『オッタートロール』の導入であり、それは全く画期的なものであったことから漁船の大型化は加速した。まずは124㌧型船への移行であるが、これに伴ない網揚げが船尾方式となり、二層甲板ともなったことから、操業効率と積載量は格段に増し、安全性も高まった。次にオッタートロールについては、省力化による人員の削減と操業可能な海域の拡大が図られたことが挙げられ(オッタートロールは、かけまわしに比べて人員が2~3名少なくて済み、また、網口を一定に開いて保てるため、長く引くことができて早く底に沈むなど、駆け上がりや深い底にも対応が出来る)、このオッタートロールを導入したのは、昭和45年の宗谷と紋別に始まり、同47年には、地元で14隻が操業している。 しかし、紋別での124㌧型への移行は、他地域よりも立ち遅れ、遠くまで出漁が出来ずに生産性も低く、よって市では沿岸漁業の保護からも沖合化を促進するため、昭和45年に建造資金の利子補給を決定し、漁協も翌年から3ヵ年の大型化計画を立てて、同49年までには、全ての底びき船が124㌧型となった。 こうして当地では、より沖合い漁場への遠隔化が図られ、昭和40年代にはズワイガニ漁が盛んとなり、同代後半にはイカナゴが多獲されるようになると水揚げは上昇に転じたが、昭和30年代後半からの不振と度重なる増トンによる借入金は、経営を圧迫した。 4紋別における戦後加工 ~加工用多獲魚の時代
戦中から漁獲対象は、高級なマガレイやタラなどから、次第に他の多獲魚へと比重を移し、質より量へとなって行く。 昭和25年の紋別の機船底びき網漁業による漁獲割合を見ると、スケソウが48.7%、ホッケは30.7%、サメ11.6%、タラ3.9%、カレイが3.1%であり、その中心は、戦前の平ものから加工原料となる丸ものへと明らかに転じている。このうちホッケは、昭和18年頃からロウソクボッケを漁獲対象としたが、統制解除の同24年以降には盛んに加工原料として用いられるようになる。 紋別の水産加工については、戦後早くに冷凍事業が開始され、また、フィッシュミールの加工が始まって、缶詰製造が復活するなどがあったが、何よりも盛んだったのは昭和20年代末頃からのスキミ加工で、同30年代には全国生産の7割強を占めるに至ったが、同24年頃からは既に開きスケソウも盛んであった。 戦中・戦後に大量に生産された焼竹輪などの練製品は、昭和20年代中頃から次第に衰えて、竹輪は同31年で姿を消したが、同35年に網走水試よって「冷凍すり身」の技術が開発され、短期間で主要な加工品となって行った(詳細後述)。また、フィッシュミールが急増したのは、同45年以降であり、同じく飼料用の冷凍イカナゴが量産されるようになった。 ズワイガニは、昭和30年代に沿岸で若干は漁獲されていたが、同39年からは道内他地域に比べても早くに本格的化され、沖合、そして遠洋へと拡大し、毛ガニに代わるカニ缶として盛んに加工されるようになった。 こうして機船底びき網漁業での主要は、スケソウとホッケに移り、イカナゴの登場もあって、水産加工業と結びつくと戦前同様に当地の産業界をリードしたが、現在に続くズワイガニの流通拠点としての性格は、このときに始まったと思われる。 §3.オイルショックと二百カイリ規制
1ふたつのオイルショック ~表面化した魚離れ 昭和48年に起こった第4次中東戦争に伴う第1次オイルショックと、同54年のイラン革命による第2次オイルショックは、単に燃油の高騰だけではなく、これ以降の漁業資材ほかの経常的な経費を押し上げ、魚価は乱高下して、漁業経済を混乱させた。 まずは第1次オイルショックであるが、このときは10月半ばから年末迄のわずか2ヶ月弱の間に、原油価格が大よそ4倍にまで上昇し、石油関連はもちろん、それ以外のあらゆる物価も高騰して、国内に猛烈なインフレーションが巻き起こった。しかし、当地では、魚価の上昇があり、翌49年と50年が好漁であったこともあって、また、漁場も比較的に近い地の利があり、他地域に比べては、小さな被害に止まった。 つづいての第2次オイルショックは、原油価格1バレルが、13ドルから32ドルまでに高騰、しかし、前回の教訓から国内経済は冷静に対応し、このときも魚価の上昇が見られたので、短期的には大きな混乱とはならなかったが、この2つのオイルショックを経て、以前に比べてコストは大きく上昇し、特に遠洋漁業への影響は、大きなものであった(沖合との兼業あり)。 そして何より、むしろ問題となるのは、実質的な可処分所得が減少する中での相対的な魚価高であり、静かに進行していた魚離れが、これによって大きく顕在化することになる。 2二百カイリ時代 ~専管水域の設定 米ソの漁業規制は、次第に強化されてはいたが、昭和52年に相ついで米ソ両国が、200カイリ漁業専管水域を宣言し、これに我国も対抗して水域を設定したことで、漁業は200カイリ規制の時代へと入る。3月末日には、ソ連(ロシア)200カイリ水域から退去することとなり、これまでの北洋海域からの撤退を余儀なくされた。 これらにより米・ソ水域とベーリング公海などの対日割当や操業海域は縮小され、同年、全国で沖合い底びき網漁船50隻を減船することになり、うち北海道で計37隻減、紋別では2隻減(建造替えを当てたので実質1隻の減)となり、沖合底びき網漁業は17隻体制となった。 この年は魚価高もあり、どうにか乗り切ることが出来たが、翌年にはほとんどの漁船が赤字に転落し、それに事業継続者には、減船共補償金約2千数百万の負担が加わって、経営は非常に逼迫した。 3主要魚種の変遷 ~冷凍すり身の功罪 それまでは鮮度が低下しやすく、蒲鉾などの練物にも向いていないと云われて、もっぱら「開き」などの乾物や塩蔵にするほかなかった「スケソウ」であったが、昭和35年に北水試のグループによって、まったく新しい加工としての「冷凍すり身」が開発(昭和38年に特許出願登録)されたことは、水産練り製品の一大発展へとつながった。 当時の業界では、以西での蒲鉾などの練物用原料が不足しており、また、魚肉ハム・ソウセージとも結びついて、「冷凍すり身(陸上すり身)」の生産は急速に広まった。昭和40年には、大手の日本水産㈱が洋上の加工船による「冷凍すり身(洋上すり身)」の生産を開始し、翌年には大洋漁業㈱が洋上すり身へ乗り出して、さらに生産量は急増し、以後のスケソウの消流を支えることになった。 このうちの洋上すり身については、昭和62年で米国の対日漁獲割当が廃止と決まり、それにかわって日米JV船からの洋上買付けが行われるようになったが、これも平成3年には廃止されて、現在は日米JVによる洋上すり身加工へとなり、この洋上での鮮度が高く、良質なすり身が大量に日本国内へ流入したことで、陸上すり身の価格が低下し、これがスケソウ価格の低迷の一因ともなり、近年は、漁獲量が比較的に安定したホッケのすり身加工が増えている。 また、主に飼料用として冷凍加工される「オオナゴ」は、当市でも「オッタートロール」を中心にピーク時で約4万トンを水揚げしたが、海域の規制と資源の減少から激減し、この直近では平成19年が約850㌧、平成20年3㌧、平成21年は約1,500㌧と低迷している。 そして地元産のズワイガニも、この10年間では、平成12年の1,015㌧をピークに、ここ数年は300㌧内外にとどまっており、もちろん、資源の低下はあっても安価なロシアからの輸入ガニに押されてのものである。 4規制強化と沖合漁業の忍従時代 ~沖合い底びき漁船の大減船と現況 さらに昭和60年に米国が、日本のベーリング海での操業停止を通告、同62年までには、米国の対日漁獲割当が廃止となって、このような米・ソ(ロシア)200カイリ水域での漁業規制の強化に伴い、我国の北洋漁業は、伝統的な漁場からの撤退、縮小を余儀なくされ、一時期は公海での操業も禁止されるなどもあり、昭和61年の国際減船では、道内の沖合い底びき網漁船が161隻から88隻となり、このときも前回同様の共補償が実施され、平成10年からは基幹漁業総合再編推進事業によって、順次、縮減されて現在は全道48隻体制となっている。 当市においても昭和63年に母船式サケ・マス漁が終結し、平成6年を最後に入会での沖合い底びき網漁業が、同11年には遠洋漁業が終焉して、地元根拠の沖合い底びき網漁業も昭和60年と翌61年の大減船を経て9隻体制となり、また、このときに道内ではじめての沖合い底びき網漁業の減船倒産が当地で発生、この間に漁船の更新期に迫られて新造船を建造するなどもあって、現在は、160㌧型を中心とした「オッタートロール」は2隻、「かけまわし」が2隻の計4隻が非常に厳しい操業を強いられている。 その後のバブル崩壊を経て、今また当市の沖合い底びき網漁船は、更新期を迎えているが、もっとも新しい船で昭和63年の建造であり、古いものでは30年目を迎え、近々では、数年前に短期的な豊漁と魚価高はあったものの、第3次オイルショックとも云われる石油製品の異常な高騰と、流通、為替を含めたいっそうの国際化から来る魚価の乱高下、リーマンショック以降の極度の経済停滞などから体力を喪失し、特に「オッタートロール」は不振を極めて、代船の建造は難しい状況にある。 しかし、ロシア国内でのさらなる漁業規制の強化は、カニ輸入の漸減として現われ、また、水産物価格の国際市場での混乱、日本の「買い負け」を考えるとき、特に多獲魚の国内での加工用原料としての重要度は、ますます増すばかりであって、漁業と加工を合わせた水産業を基盤とする当市においては、沖合い底びき網漁業を維持することが直近の重要課題と云える。 このように目まぐるしく変わる国内外の漁業環境の変化に対応した政策に翻弄されながらも、沖合い底びき網漁業は、紋別市の産業界の基盤となり、その後もリードしながらマチの発展に大きく寄与して来た。





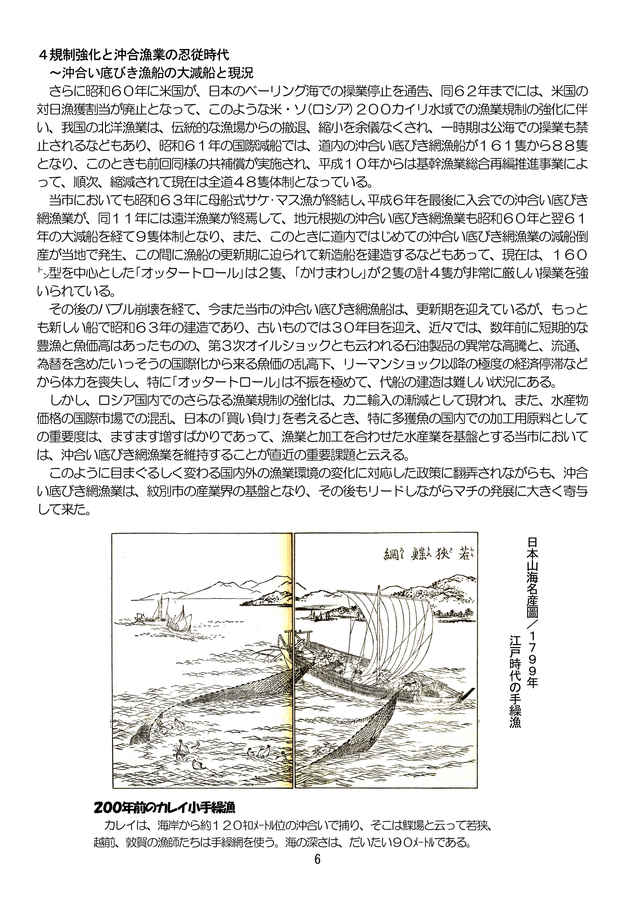 戦前の紋別港 当時、最新鋭だった松田冷蔵庫 戦後、間もない頃の小手繰船 昭和32年頃、出港の景、霧笛 沖底船の水揚げ、春ホッケ、追いニシン 日本山海名産圖/江戸時代の手繰漁、200年前のカレイ小手繰漁 カレイは、海岸から約120キロメートル位の沖合いで捕り、そこは鰈場と云って若狭、越前、敦賀の漁師たちは手繰網を使う。海の深さは、だいたい90メートルである。 紋別を例とした沖合底びき漁船と水産加工の歴史 §1.機船底びき網漁業の興り 1沖合底びき網漁業の勃興 ~動力船の登場 単に「機船」と呼ぶとき、それは「底びき網漁船」のことを示すが、我国における近代的な沖合底びき網漁業は、明治36年に輸入された機船トロールに始まると云う、底びき網漁業は平安末期の1087年の記録『能登浦領内ノ事』に「北ハカレイ引ヲ定也」とあり、若狭湾では、寛文期以前から「沖手繰による鰈引き」が盛んであった。 この若狭湾での明治43年の試験操業は失敗に終わったが、続いて大正2年に島根県で始まった沖手繰は、漸次、成績を上げると四国地方、そして日本海の各地へと広まった。 北海道では、明治38年の室蘭での試験操業が最初と云われ、同41年には8隻の底びき網機船があったとも云う。後年、同漁業の中心地となった小樽では、大正元年に始めて試みられたが、この時には定着しなかった。 後に道内において継続的な経済操業に至ったのは大正の中期以降の小樽や函館であり、大正9年の底びき網機船の登録は、小樽100、岩内10、函館4、室蘭33、釧路52、根室3、宗谷1、留萌12の計215隻であったが、実際の操業は100隻程度だった。 道庁では、この様ににわかに勃興した底びき網機船を、夏枯れに対応した通年操業とするため、大正9年から翌10年にかけてオホーツク海の漁場調査を行い、同12年と14にはトロール試験を実施して、新開の北見漁場へと誘導した。 2紋別でのはじまり ~第三寅丸の回航 紋別では、明治36年頃から無動力の川崎船によるカレイ小手繰が行われていて、大正年間には紋別の一本松から興部の砂留の間で2~3隻が操業していたと云うが、加工・流通の未発達な時代にあっては振るわなかった。 当地での最初の動力船は、紋別漁協が大正3年に導入したホタテ監視船であったが、数年後には、それを高嶋春松が購入して、紋別~湧別間の輸送を行いながらマガレイ漁をはじめたと云い、これが網走管内の底びき網機船の始まりであった。 こうして紋別でも漁業近代化の波が現れ、大正12年には小樽から松田鉄蔵の機船「第三寅丸」が回航してマガレイを大漁し、鮮魚は主に旭川方面へ販売して、あとはカマボコや魚粕などに加工した。また、同年に地元では伴田惣十郎が機船2隻を建造し、翌年には操業を始めた。 3紋別水産界の発展 ~近代的水産業の現れ
戦前の紋別港 当時、最新鋭だった松田冷蔵庫 戦後、間もない頃の小手繰船 昭和32年頃、出港の景、霧笛 沖底船の水揚げ、春ホッケ、追いニシン 日本山海名産圖/江戸時代の手繰漁、200年前のカレイ小手繰漁 カレイは、海岸から約120キロメートル位の沖合いで捕り、そこは鰈場と云って若狭、越前、敦賀の漁師たちは手繰網を使う。海の深さは、だいたい90メートルである。 紋別を例とした沖合底びき漁船と水産加工の歴史 §1.機船底びき網漁業の興り 1沖合底びき網漁業の勃興 ~動力船の登場 単に「機船」と呼ぶとき、それは「底びき網漁船」のことを示すが、我国における近代的な沖合底びき網漁業は、明治36年に輸入された機船トロールに始まると云う、底びき網漁業は平安末期の1087年の記録『能登浦領内ノ事』に「北ハカレイ引ヲ定也」とあり、若狭湾では、寛文期以前から「沖手繰による鰈引き」が盛んであった。 この若狭湾での明治43年の試験操業は失敗に終わったが、続いて大正2年に島根県で始まった沖手繰は、漸次、成績を上げると四国地方、そして日本海の各地へと広まった。 北海道では、明治38年の室蘭での試験操業が最初と云われ、同41年には8隻の底びき網機船があったとも云う。後年、同漁業の中心地となった小樽では、大正元年に始めて試みられたが、この時には定着しなかった。 後に道内において継続的な経済操業に至ったのは大正の中期以降の小樽や函館であり、大正9年の底びき網機船の登録は、小樽100、岩内10、函館4、室蘭33、釧路52、根室3、宗谷1、留萌12の計215隻であったが、実際の操業は100隻程度だった。 道庁では、この様ににわかに勃興した底びき網機船を、夏枯れに対応した通年操業とするため、大正9年から翌10年にかけてオホーツク海の漁場調査を行い、同12年と14にはトロール試験を実施して、新開の北見漁場へと誘導した。 2紋別でのはじまり ~第三寅丸の回航 紋別では、明治36年頃から無動力の川崎船によるカレイ小手繰が行われていて、大正年間には紋別の一本松から興部の砂留の間で2~3隻が操業していたと云うが、加工・流通の未発達な時代にあっては振るわなかった。 当地での最初の動力船は、紋別漁協が大正3年に導入したホタテ監視船であったが、数年後には、それを高嶋春松が購入して、紋別~湧別間の輸送を行いながらマガレイ漁をはじめたと云い、これが網走管内の底びき網機船の始まりであった。 こうして紋別でも漁業近代化の波が現れ、大正12年には小樽から松田鉄蔵の機船「第三寅丸」が回航してマガレイを大漁し、鮮魚は主に旭川方面へ販売して、あとはカマボコや魚粕などに加工した。また、同年に地元では伴田惣十郎が機船2隻を建造し、翌年には操業を始めた。 3紋別水産界の発展 ~近代的水産業の現れ前述の以降は、夏枯れ対策として小樽・室蘭・留萌からも多くの機船が回航し、紋別を根拠地に常時15・6隻以上が、主に雄武から興部沖の浅いところで35~50㍍、深いところでは60~80㍍の範囲でマガレイを大漁したが、昭和15年頃までの地元の登録船は、松田2、伴田2、浜田・上森・太田が各1の計7隻で一定した。 昭和11年の千島も含めた全漁獲高では、紋別が全道市町村中で第5位にあり、その内のカレイ漁は3位で、底引き網での同漁はダントツの1位であった。 当時は、既に地元の仲買人はいたが(大正4年に紋別魚市場が開設)、大きな取引は主に小樽の問屋衆で占められていて、季節的に大漁されるマガレイなどは、価格が不安定であり、この頃には、底びき網の船主が大きなカレイは自ら東京へ送ったりもしたが、うまく届くと大儲け、途中で腐ると丸損という有り様だった。 この鮮魚の出荷には、その前提となる冷蔵庫が必要であり、すでに大正年間には2つの貯氷庫があり、昭和5年には松田鉄蔵と松崎隆一による全道でも2番目の当時としては最新式の冷蔵庫が建設されたが、築地市場への鮮魚特急と呼ばれた冷蔵貨車は、その台数が限られており、昭和14年に「北海道機船底曳網漁業水産組合紋別支部」が発足し、同じく「紋別機船底曳網漁業出荷組合」を結成して、共同での発送を行った。 これら機船底びき網漁業によるマガレイ漁と、それにかかる冷凍・冷蔵技術の導入など、鮮魚流通に向けた努力は、築地や小田原、札幌などへの地方出荷となり、後の「もんべつマガレイ」ほか、地元海産物の産地ブランドへと繋がって行く。 §2.機船底びき網漁業の転換と戦後の加工業 1底びき網漁業の濫立と停滞 ~沿岸漁業の荒廃 特に北海道では、昭和初期に急激な漁船数の増加を見たが、これは単に底びき網機船の隻数が増えたのであり、漁船自体の大型化は伴わずに密漁が横行し、それは資源の乱獲と沿岸漁業者との紛争を招くことになり、戦時の燃油・資材の不足もあって中型の底びき網機船自身も採算が取れない状況に陥ってしまった。 当地においても、マガレイのほかに昭和2年頃からはアブラザメ漁も始めてはいたが、同8年頃から特にカレイ類の資源減少が現れ、同12年からはタラ、スケソウを漁獲するようになり、これらの加工はサメヒレなどの乾物と一部が練物とされたほかは、主に魚油や魚粕とした。 こうして遂に昭和5年には「機船底曳網漁業取締規則」が改定され、規制の強化が図られることになったが、戦時の食料確保と徴用船への対応から規制は次第に緩慢となり、結局、これらによって漁業制度は崩壊してしまう。
いっぽう、昭和16年からの統制経済は脱仕込ともなり、食糧不足の中で一定の価格が維持されたことから、小規模漁業者の負債は整理され、また、それまで廉価であったホッケが脚光をあびるようになるなどの副産物を生んだ。 しかし、戦後に至って食料不足がいっそう深刻化すると、乱獲による資源の減少は著しいものとなり、また、紋別でも昭和27年を最後にニシンの群来が見られなくなるなど、かえって漁獲効率が高い小手繰船を増加させ、密漁船が横行するという悪循環となってしまった。 2底びき網漁業の戦後処理 ~小中底びき船の整理 小型機船底びき網漁業(小手繰船)は、昭和19年に10㌧未満を限り合法としたが、実際には20㌧前後も黙認され、さらに戦後に千島海域を失った底びき船が入り込んで沿岸資源の減少が深刻となり、沿岸漁業との摩擦が拡大されると、底びき船は、より沖合への出漁を余儀なくされ、沿岸から沖合いへ、沖合いから遠洋へと船の大型化・近代化が図られるようになったが、沖合底びき網漁業の採算は難しく、後にそれは北洋操業へと転換して行く。 昭和23年に、35㌧未満が35㌧へ、35㌧から40㌧未満は40㌧に、そして40㌧から45㌧未満が45㌧への増トンを認めて、実測との補正を行い、同25年には北海道庁が、小手繰船の整理と無許可船の根絶を図るため、小手繰網漁船の許可船4隻に対して1隻の中型底びき網漁船への転換と、無許可船は8隻から1隻の中型底びき網漁船への転換を指導した。 昭和26年における紋別根拠の中型機船底びき網漁業の登録数(入会、2箇所登録有り)は61隻あり、その船籍は紋別(21)、網走(9)、函館(8)、根室(6)、小樽(5)、東京(5)、興部(3)、湧別(3)、雄武(1)とあり、主要な経営主としては、東京の日東水産㈱が6隻、小樽の松田関連の5隻(大成2、辰蔵2、松田漁業1)などがあった。この年には機船底びき網の15㌧未満を小型、それ以上から60㌧までが中型と定められ、のち北海道と東北に限り、木船75㌧、鋼船85㌧までとされた。 3機船漁業の転換 ~漁船の大型化、より沖合いへ 昭和27年にマッカーサーラインが撤廃され、戦後の日本の遠洋漁業が解禁された。昭和29年には『沿岸から沖合いへ、沖合いから遠洋』への政策が固まり、それまで地方で行われていた新開漁場の開発が国の事業となり、ベーリング海域などで遠洋底びき試験操業が開始されて、同30年から紋別へも水揚されるようになると、同32年には紋別船も出漁を開始した。 昭和31年には、これら新開漁場への出漁や他の漁業との兼業など、季節的に沖合底びき網漁業を行わない船の増トンが認められ、このような経緯の中で当地を主な根拠地とする昭和26年の操業船が48隻であったものが、同35年には35隻に減少した一方で、70㌧以上が5隻出現した。昭和36~38年にかけては全道で沖合底びき網漁業を大減船し、一部を北洋底びき網漁業へ転換。紋別では6隻が減船し、うち1隻が転換した(北転船と云う)。 そうして昭和37年からは船員の労働環境の改善を目的とした96㌧型への増トンが図られると、漁船の大型化は急激に進行し、この間、沖合底びき網漁業は、北海道で最も安定した漁業となっていたが、昭和30年代末をピークに漁獲量が下向を示し、同40年代に入って徐々に漁価が低下しだすと、人手不足もあいまって深刻な経営不振に陥ってしまった。紋別でも昭和43年の着業者は21事業者、24隻となっていた。 こうした状況下で打開策とされたのが『124㌧型船』への移行と『オッタートロール』の導入であり、それは全く画期的なものであったことから漁船の大型化は加速した。まずは124㌧型船への移行であるが、これに伴ない網揚げが船尾方式となり、二層甲板ともなったことから、操業効率と積載量は格段に増し、安全性も高まった。次にオッタートロールについては、省力化による人員の削減と操業可能な海域の拡大が図られたことが挙げられ(オッタートロールは、かけまわしに比べて人員が2~3名少なくて済み、また、網口を一定に開いて保てるため、長く引くことができて早く底に沈むなど、駆け上がりや深い底にも対応が出来る)、このオッタートロールを導入したのは、昭和45年の宗谷と紋別に始まり、同47年には、地元で14隻が操業している。 しかし、紋別での124㌧型への移行は、他地域よりも立ち遅れ、遠くまで出漁が出来ずに生産性も低く、よって市では沿岸漁業の保護からも沖合化を促進するため、昭和45年に建造資金の利子補給を決定し、漁協も翌年から3ヵ年の大型化計画を立てて、同49年までには、全ての底びき船が124㌧型となった。 こうして当地では、より沖合い漁場への遠隔化が図られ、昭和40年代にはズワイガニ漁が盛んとなり、同代後半にはイカナゴが多獲されるようになると水揚げは上昇に転じたが、昭和30年代後半からの不振と度重なる増トンによる借入金は、経営を圧迫した。 4紋別における戦後加工 ~加工用多獲魚の時代
戦中から漁獲対象は、高級なマガレイやタラなどから、次第に他の多獲魚へと比重を移し、質より量へとなって行く。 昭和25年の紋別の機船底びき網漁業による漁獲割合を見ると、スケソウが48.7%、ホッケは30.7%、サメ11.6%、タラ3.9%、カレイが3.1%であり、その中心は、戦前の平ものから加工原料となる丸ものへと明らかに転じている。このうちホッケは、昭和18年頃からロウソクボッケを漁獲対象としたが、統制解除の同24年以降には盛んに加工原料として用いられるようになる。 紋別の水産加工については、戦後早くに冷凍事業が開始され、また、フィッシュミールの加工が始まって、缶詰製造が復活するなどがあったが、何よりも盛んだったのは昭和20年代末頃からのスキミ加工で、同30年代には全国生産の7割強を占めるに至ったが、同24年頃からは既に開きスケソウも盛んであった。 戦中・戦後に大量に生産された焼竹輪などの練製品は、昭和20年代中頃から次第に衰えて、竹輪は同31年で姿を消したが、同35年に網走水試よって「冷凍すり身」の技術が開発され、短期間で主要な加工品となって行った(詳細後述)。また、フィッシュミールが急増したのは、同45年以降であり、同じく飼料用の冷凍イカナゴが量産されるようになった。 ズワイガニは、昭和30年代に沿岸で若干は漁獲されていたが、同39年からは道内他地域に比べても早くに本格的化され、沖合、そして遠洋へと拡大し、毛ガニに代わるカニ缶として盛んに加工されるようになった。 こうして機船底びき網漁業での主要は、スケソウとホッケに移り、イカナゴの登場もあって、水産加工業と結びつくと戦前同様に当地の産業界をリードしたが、現在に続くズワイガニの流通拠点としての性格は、このときに始まったと思われる。 §3.オイルショックと二百カイリ規制
1ふたつのオイルショック ~表面化した魚離れ 昭和48年に起こった第4次中東戦争に伴う第1次オイルショックと、同54年のイラン革命による第2次オイルショックは、単に燃油の高騰だけではなく、これ以降の漁業資材ほかの経常的な経費を押し上げ、魚価は乱高下して、漁業経済を混乱させた。 まずは第1次オイルショックであるが、このときは10月半ばから年末迄のわずか2ヶ月弱の間に、原油価格が大よそ4倍にまで上昇し、石油関連はもちろん、それ以外のあらゆる物価も高騰して、国内に猛烈なインフレーションが巻き起こった。しかし、当地では、魚価の上昇があり、翌49年と50年が好漁であったこともあって、また、漁場も比較的に近い地の利があり、他地域に比べては、小さな被害に止まった。 つづいての第2次オイルショックは、原油価格1バレルが、13ドルから32ドルまでに高騰、しかし、前回の教訓から国内経済は冷静に対応し、このときも魚価の上昇が見られたので、短期的には大きな混乱とはならなかったが、この2つのオイルショックを経て、以前に比べてコストは大きく上昇し、特に遠洋漁業への影響は、大きなものであった(沖合との兼業あり)。 そして何より、むしろ問題となるのは、実質的な可処分所得が減少する中での相対的な魚価高であり、静かに進行していた魚離れが、これによって大きく顕在化することになる。 2二百カイリ時代 ~専管水域の設定 米ソの漁業規制は、次第に強化されてはいたが、昭和52年に相ついで米ソ両国が、200カイリ漁業専管水域を宣言し、これに我国も対抗して水域を設定したことで、漁業は200カイリ規制の時代へと入る。3月末日には、ソ連(ロシア)200カイリ水域から退去することとなり、これまでの北洋海域からの撤退を余儀なくされた。 これらにより米・ソ水域とベーリング公海などの対日割当や操業海域は縮小され、同年、全国で沖合い底びき網漁船50隻を減船することになり、うち北海道で計37隻減、紋別では2隻減(建造替えを当てたので実質1隻の減)となり、沖合底びき網漁業は17隻体制となった。 この年は魚価高もあり、どうにか乗り切ることが出来たが、翌年にはほとんどの漁船が赤字に転落し、それに事業継続者には、減船共補償金約2千数百万の負担が加わって、経営は非常に逼迫した。 3主要魚種の変遷 ~冷凍すり身の功罪 それまでは鮮度が低下しやすく、蒲鉾などの練物にも向いていないと云われて、もっぱら「開き」などの乾物や塩蔵にするほかなかった「スケソウ」であったが、昭和35年に北水試のグループによって、まったく新しい加工としての「冷凍すり身」が開発(昭和38年に特許出願登録)されたことは、水産練り製品の一大発展へとつながった。 当時の業界では、以西での蒲鉾などの練物用原料が不足しており、また、魚肉ハム・ソウセージとも結びついて、「冷凍すり身(陸上すり身)」の生産は急速に広まった。昭和40年には、大手の日本水産㈱が洋上の加工船による「冷凍すり身(洋上すり身)」の生産を開始し、翌年には大洋漁業㈱が洋上すり身へ乗り出して、さらに生産量は急増し、以後のスケソウの消流を支えることになった。 このうちの洋上すり身については、昭和62年で米国の対日漁獲割当が廃止と決まり、それにかわって日米JV船からの洋上買付けが行われるようになったが、これも平成3年には廃止されて、現在は日米JVによる洋上すり身加工へとなり、この洋上での鮮度が高く、良質なすり身が大量に日本国内へ流入したことで、陸上すり身の価格が低下し、これがスケソウ価格の低迷の一因ともなり、近年は、漁獲量が比較的に安定したホッケのすり身加工が増えている。 また、主に飼料用として冷凍加工される「オオナゴ」は、当市でも「オッタートロール」を中心にピーク時で約4万トンを水揚げしたが、海域の規制と資源の減少から激減し、この直近では平成19年が約850㌧、平成20年3㌧、平成21年は約1,500㌧と低迷している。 そして地元産のズワイガニも、この10年間では、平成12年の1,015㌧をピークに、ここ数年は300㌧内外にとどまっており、もちろん、資源の低下はあっても安価なロシアからの輸入ガニに押されてのものである。 4規制強化と沖合漁業の忍従時代 ~沖合い底びき漁船の大減船と現況 さらに昭和60年に米国が、日本のベーリング海での操業停止を通告、同62年までには、米国の対日漁獲割当が廃止となって、このような米・ソ(ロシア)200カイリ水域での漁業規制の強化に伴い、我国の北洋漁業は、伝統的な漁場からの撤退、縮小を余儀なくされ、一時期は公海での操業も禁止されるなどもあり、昭和61年の国際減船では、道内の沖合い底びき網漁船が161隻から88隻となり、このときも前回同様の共補償が実施され、平成10年からは基幹漁業総合再編推進事業によって、順次、縮減されて現在は全道48隻体制となっている。 当市においても昭和63年に母船式サケ・マス漁が終結し、平成6年を最後に入会での沖合い底びき網漁業が、同11年には遠洋漁業が終焉して、地元根拠の沖合い底びき網漁業も昭和60年と翌61年の大減船を経て9隻体制となり、また、このときに道内ではじめての沖合い底びき網漁業の減船倒産が当地で発生、この間に漁船の更新期に迫られて新造船を建造するなどもあって、現在は、160㌧型を中心とした「オッタートロール」は2隻、「かけまわし」が2隻の計4隻が非常に厳しい操業を強いられている。 その後のバブル崩壊を経て、今また当市の沖合い底びき網漁船は、更新期を迎えているが、もっとも新しい船で昭和63年の建造であり、古いものでは30年目を迎え、近々では、数年前に短期的な豊漁と魚価高はあったものの、第3次オイルショックとも云われる石油製品の異常な高騰と、流通、為替を含めたいっそうの国際化から来る魚価の乱高下、リーマンショック以降の極度の経済停滞などから体力を喪失し、特に「オッタートロール」は不振を極めて、代船の建造は難しい状況にある。 しかし、ロシア国内でのさらなる漁業規制の強化は、カニ輸入の漸減として現われ、また、水産物価格の国際市場での混乱、日本の「買い負け」を考えるとき、特に多獲魚の国内での加工用原料としての重要度は、ますます増すばかりであって、漁業と加工を合わせた水産業を基盤とする当市においては、沖合い底びき網漁業を維持することが直近の重要課題と云える。 このように目まぐるしく変わる国内外の漁業環境の変化に対応した政策に翻弄されながらも、沖合い底びき網漁業は、紋別市の産業界の基盤となり、その後もリードしながらマチの発展に大きく寄与して来た。
Posted by 釣山 史 at 21:00│Comments(0)
│紋別の歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。









